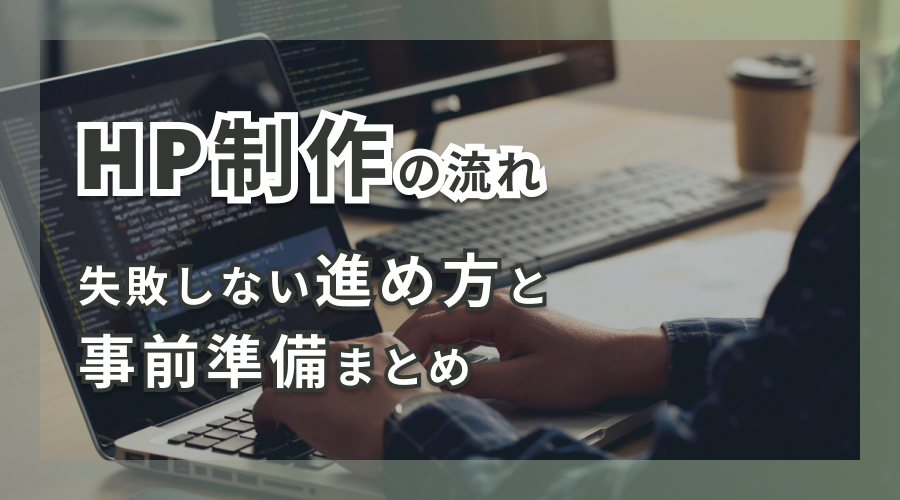ホームページを持つことは、企業にとって当たり前のようになりました。ホームページがあれば、世界中の人たちに自社を知ってもらうことができます。
また、高額な広告費を使わなくても半永続的にユーザーに知ってもらう機会を得ることができます。
ですが、どうすればホームページを制作できるのか、どのような流れで制作すべきなのかは知識や経験がないと難しいですよね。
そこで、ホームページ制作の基本的な流れについて解説します。ぜひ、参考にしてください。
目次
ホームページ制作の企画段階で明確にする3つのこと

ホームページ制作は、コンセプトや方向性などを決める企画から始まります。
企画が疎かになってしまうと、統一感のないホームページになってしまったり、工数が増えて想定以上にコストがかかってしまったりします。また、スタート地点で方向性がずれてしまうと、成果物が求めるものに対して大きな乖離ができてしまいます。
そのため、企画は非常に重要なステップです。そこでまずは、企画段階で何を決めるべきなのか、何を意識するべきなのかを紹介します。
ホームページ制作で得たい成果を明確にする
ホームページ制作で最初に考えるべきは「何のために作るのか」「ホームページを作ることで何を得たいのか」です。
例えば、企業について網羅的に伝えたい、事業内容や理念を伝えたいという時は、一般的な企業Webサイトでいいでしょう。ですが、商品の魅力を伝えたいなら、LP(ランディングページ)を制作するという選択肢もあります。
また、ホームページで得たいのが新規顧客なのか、既存顧客の定着なのか、もしくは採用なのかも決めておく必要があります。それによって、メッセージの内容やコンテンツの数、デザイン性、ページ遷移の導線などが変わってきます。
もちろん、全てを獲得したいという考えもあります。ですが、その中でも優先順位は必要です。
もし目的や優先順位が不明確だと、制作時の方向性がブレやすく、成果が期待できません。そのため、目的を明確にすることは、Webサイト制作の成功の鍵となります。
どのような人に見てもらいたいかを明確にする
ホームページを制作するときは、どのようなユーザーがターゲットなのかを決めておくことも大切です。
例えば、会社のことを知らない新規顧客に見てもらいたいのか、既存顧客に見てもらいたいのか、それは法人向けなのか個人向けなのか、もしくは採用や働く人へのメッセージを重視したいかなども決めておくことが必要です。
もちろん、これはビジネスモデルによっても異なるでしょう。また、この時にペルソナを設定しておくとより明確に訪れるユーザーをイメージしやすくなります。
ペルソナとは、ターゲットをさらに具体的にしたキャラクターのこと。彼や彼女の学歴、趣味、休日の過ごし方など、生活の詳細まで想像して設定します。
これらのターゲットとペルソナを設定することで、ホームページの方向性がブレにくくなります。具体的に想像することで、サイトの内容やデザイン、使いやすさなど、全てがお客さん目線で作ることができるのです。
競合の調査・分析し自社サイトのコンセプトを決める
ホームページに求める成果やターゲットを明確にしたら、競合他社がどのようなホームページを作成しているのかを調査・分析します。
特に注目したいのは、各社の共通するコンテンツやそれぞれの強み・弱み、そして自社が戦うべき土俵がどこかというところです。これらの情報を調査・分析することで、効果的なサイトの設計やコンセプトが浮かび上がります。
さらに、ライバルのマーケティング活動や、他のSNSやWeb広告との連携方法も調査すると、有益な情報を得ることができます。
ホームページを作成するときは、ユーザーの印象に残ることが大切です。もし、作成したい方向性が他と似通っていたり埋もれてしまうと、公開後に効果を出しにくくなるかもしれません。
それを避けるためにも、ヒアリングや市場調査を行い、自社の強みやユーザーニーズを明確にすることが大切です。
そして、分析した上でサイト制作の大きな指針となるコンセプトを決めます。このコンセプトは、サイトのデザインや内容、機能の方針を示す重要なガイドラインとなります。
ホームページ制作には多くのステップが存在しますが、それぞれのステップでしっかりと調査や分析を行うことで、成功への道が開けるでしょう。
ホームページのコンテンツ制作・公開の4STEP

企画段階が終わったら、実際にコンテンツの制作を行います。ただし、コンテンツ制作も一つ一つ段階を経ていかないと漏れが出てしまったり、質の低いコンテンツが生まれてしまったりします。
ここでは、どのようなステップを踏めばもれなくコンテンツを制作できるか、より質の高いページになるかを解説します。
一つ一つクリアして、満足いくホームページを制作していきましょう。
サイトマップを作成する
他サイトの調査が終わり、自社ホームページのコンセプトが定まったら、どのようなページを作成するのかを明確にします。そして、その上で「サイトマップ」を作成します。
サイトマップとは、サイトの全体図です。どのようなページがあり、それらのページがどのようにカテゴライズされ、リンクが繋がるのかを明確にします。
サイトマップがあることで作成すべきページが誰にでもわかるようになりますし、必要ページの制作漏れがなくなります。
また、ページごとの関係性を明確にすることでユーザーの回遊のしやすさや満足度が高められます。知りたい情報が掲載されているページがしっかりとリンクで繋がっていると、ユーザーは利便性が上がるのです。
そうした繋がりを客観的に見るためにも、サイトマップを作成することが大切です。
各ページのワイヤーフレームを制作する
サイトマップを作成してホームページの全体像を明確にしたら、各ページを制作していきます。その際にまず作成するのがワイヤーフレームです。
サイトマップがサイト全体の設計図なのであれば、ワイヤーフレームはページの設計図。どこに画像をおいてどこにテキストをおくか、表は入れるかなど、大まかな枠組みを作ります。
ワイヤーフレームを作成することで関係者が共通認識を持つことができますし、軌道修正も容易になります。
テキストやデザインの制作・コーディング
ワイヤーフレームを制作したら、実際にコンテンツを制作します。テキストや文字装飾、画像、表、グラフなどを制作しながら、ページを完成させていきます。
制作する際は、はじめに定めたコンセプトに基づいて行うことで各ページの統一感を保てます。
また、各ページはHTMLやCSS、時にはJavaScriptなども活用してWEB上で見れるようにファイルを作成していきます。また、ファイルが完成したらサーバーを用意してファイルをアップロードしていきます。
なお、全てゼロから構築するのは非常に労力と知識が必要になるため、CMSと呼ばれるツールを使用するのが一般的です。有名なのはWordPressですが、それ以外にも様々なCMSがありますので、自社にあったツールを使用するのが大切です。
さらに、GoogleTagManagerのような外部のサービスとの連携を設定することもあります。これにより、Webサイトがより魅力的になり、運用も便利になります。
ホームページを公開する
必要なページを制作しサーバーにアップしたら、公開前に内容の確認を行います。想定通りにページが動き、遷移しているか、誤字や情報の正確性、スマホ表示の確認、お問い合わせ機能の動作に問題がないかなど、細かなポイントをしっかりとチェックします。
公開前にはこれらのテストを行って問題がないことを確認した上で、実際の公開を迎えます。
また、新しいホームページを公開する際には、広報活動が欠かせません。自社SNSやプレスリリースを活用することもあるでしょう。新しいサイトの情報をしっかりと伝えることで、多くの人々が訪れるきっかけを作ることができます。
ホームページを公開した後にやるべき取り組み

ホームページは、公開しただけでは終わりではありません。公開後も日常的に運用することが非常に大切です。
サイト情報の定期的な更新や新しいコンテンツの追加、サーバーの保守など、常にホームページをメンテナンスすることで、ユーザーにまた訪れたいと思ってもらえるホームページになっていきます。
また、ホームページを更新することはSEOとしても大きな意味を持ちます。全く更新されないサイトは検索サイトから生きていないと判断され、上位に表示されなかったりします。そのため、定期的なメンテナンスが重要なのです。また、SNSと連携することも有効的です。
ホームページを制作することで、求める成果の第一歩を踏み出せます。ですが、その成果を最大限にするためには、公開後の運用も重要です。
まとめ

ホームページの制作は、進め方を誤るとコストばかりが膨らんで予定した制作物が完成しない場合があります。
ですが、制作の流れをしっかりと把握し、準備をして臨むことで成果を生み出すホームページが完成します。
しっかりと段階を踏んで作成すれば、新たな顧客や顧客の定着、そして採用の向上など、様々な成果を生み出せるようになりますよ。
ただし、より質の高いホームページを制作するには、知識や経験が必要です。そのため、制作会社に依頼する方が安心です。
その場合でも、流れを理解ししっかりと準備をしてから臨むようにしましょう。そうすることで、円滑に制作を進めていけるようになりますよ。